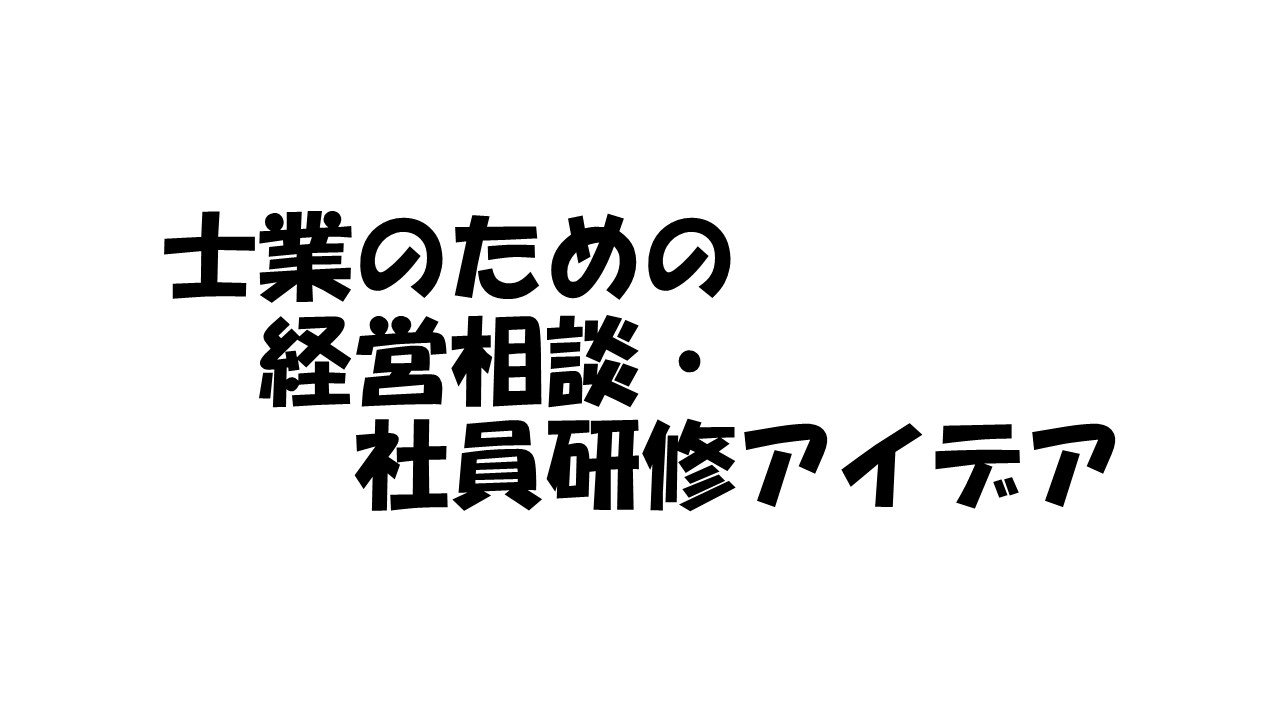「労働審判」って何ですか?
よくいただく質問の一つに,
この質問があります。
誤解をおそれず,
簡単に言ってしまえば,
労働審判は,
労働問題に限定された手続で,
しかも,普通の裁判・民事訴訟をかなり簡略化した,
ミニ裁判,プレ裁判というようなイメージです,
とお伝えしています。
詳しくお伝えすると,
ふつうの裁判,民事訴訟と比較してお伝えしますと,
民事訴訟は、テレビドラマなどでもよく見る、
公開の法廷で行う裁判手続をイメージされると思います。
だいたい、
第一審の判決が出るまで一年ほどかかり、
長いものであればさらに時間がかかります。
概ね、月に一度、
裁判期日が設定され、
最初のうちは、原告と被告の双方がお互いの主張を出し合い、
争点が明らかとなったところで
(ここまでで、少なくても
半年ほどの期間がかかっていることが多いです。)、
証人尋問を行い、
そして、裁判所が判決を言い渡すことにより、
第一審段階での結論が出るという流れになっております。
なお、争点が明らかとなった段階や、
証人尋問後の段階で、
原告と被告が譲り合って解決方法を探すために、
和解による解決を検討することがあります。
これに対して、
労働審判は、
公開の法廷では行われず、非公開で行われます。
進行スピードがとても早く、
平均審理期間は、約70日ほどと言われ、
民事訴訟と比べると驚異的な早さと言えます。
労働審判は、
申し立てから原則として40日以内に
第1回期日が設定されます。
その後も、概ね、1ヶ月ごとに期日が設定されます。
原則として、
第1回の期日で、すべての主張を行い、
証拠を提出する必要があり、
遅くとも第2回期日までに
すべての主張・立証をしておくことが望まれます。
そして、第1回から、
話し合いによる解決が試みられることが多く、
第3回の期日までに話し合いが整わない場合は、
審判という形で、
結論が言い渡されるというものです。
そうすると、
労働審判の申し立てを行う方は、
十分な準備時間があるのに対して、
労働審判の申し立てを受ける方は、
準備時間が少ないため、
申し立てを受ける方は相当な負担になると思われます。
(ただし,結論に納得できなければ,
異議の申し立てと言って,
通常の民事訴訟に移行してもらうことができます。)
そのため、労働問題のトラブルがあった際は、
労働審判の申し立てがなされることを予期して、
準備をしておく必要があります。
準備時間がない場合、
弁護士に相談をしても、
弁護士が準備時間をとれない関係で、
お役に立てないということがあります。
ちなみに、労働審判は、
事件の7割が,調停が成立しているそうで、
解決率としてもかなり高い数字であると思います。
逆に、調停が成立せず、
審判がなされた事件は、
そのうちの6割が,
異議申立てがされているそうです。
そして、よく、労働審判がダメだったら、
民事訴訟をすればいいでしょうか?という質問がございます。
しかし、労働審判の結果に対して、
不服のある当事者は、
その旨を「異議」という形、申し出ると、
当該手続きは、そのまま、民事訴訟に移行することになるのです。
これは、労働審判を申し立てた側でも、申し立てられた側でも、
どちらが異議を出しても、民事訴訟に移行するのです。
そのため、労働審判の申立てを行う場合、
審判で意図する結果を得られなかった場合、
異議を出せば訴訟に移行しますし、
訴訟までは望んでいなかったとしても、
相手方が異議を出した場合は、
やはり、訴訟に移行することを
覚悟しておかなければなりません。
逆に、労働審判で意図する結果を得られても、
相手方が異議を出せば、
やはり、民事訴訟に移行することを
覚悟しておかなければなりません。
このように、労働審判と民事訴訟の関係は、
正確に把握しておく必要があります。